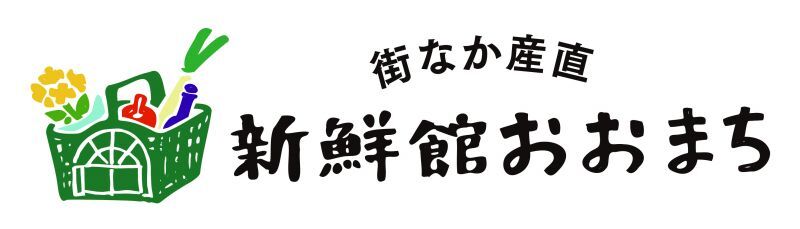大町の由来
一関の地名そのものは平泉政権時代からあったようですが、「大町」とその中心街を名付けたのは慶長10年(1604)前後、今の花泉町清水公園に城を構えていた留守(るす)政景が望んで一関に城を移す前後だったと思われます。政景は自分の領下の町屋(商店街)に大町と命名する(のちに水沢でも)人でしたから、一関移封後と断定出来ません。
その後の大町の戸数は1673年(寛文13)63戸、1775年(安永4)91戸、1838年(天保9)109戸、1868(慶応4)111戸と着実に増え続けて来るのでした。今の表通りの店舗数と江戸末期の戸数とはほとんど違いはありません。
釣山下にある藩主居館(城)に大量の敵軍が進攻しないように商店街も間口3間半(6.4M)に決められたものが、維新後100年以上の今日まで影響を与え続けて来ました。
吉田松陰の通った大町
江戸時代にはすっかり奥州街道という大動脈にあった大町でしたから、旅人は否応なしにこの道を通るのですが、その中でも歴史的な転換の役割を演じた文化人たちがここを通ったとなるとみ方を変えざるを得なくなり大町趣きも違ったものとなります。俳聖・芭蕉と頼三樹三郎(頼山陽の子)は平泉遊趣で一関に宿しましたし、幕末の志士を育てた吉田松陰師は知己の一関藩士・佐瀬氏宅を訪れ何やら話あっているようです。
今のように近代化された商店街に立ち、この3人の当時の道住く姿を想えば、新たな価値が湧いて来るのです。